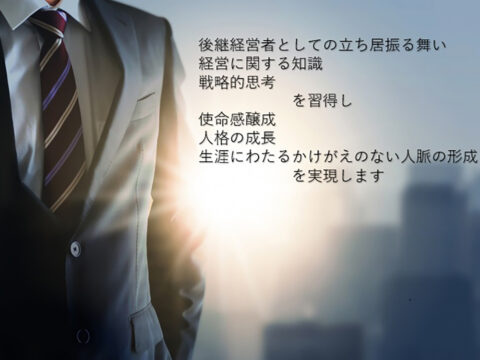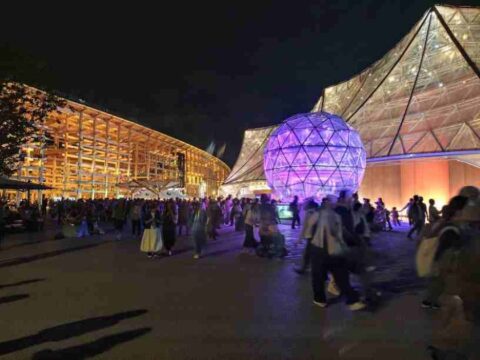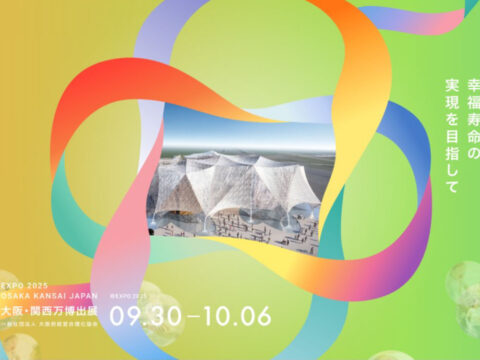「トップの決断」
地域貢献、社員への思いが決断力の下地に
大きな幸運を招き、成長路線をひた走る
三進金属工業株式会社
代表取締役社長
新井宏昌氏

■最大の決断、2001年福島県に大プロジェクト
当社は1964年11月に創業、昨年60周年を迎えました。決算が9月なので、直近の2024年9月末の売り上げは277億円、経常利益15億円。社員数は637名、東西に工場を持ち、ラック製造能力日本一を掲げています。
年間鋼材の使用量は5万トン以上、自他ともに認めるラック製造能力日本一の工場です。販売拠点は全国に20数ヵ所、海外では韓国・ベトナム・タイの3ヵ国に拠点を設け、棚板1枚、仕切り板1枚をしっかりと供給する、物流保管設備を主に製造販売している会社です。
本日のテーマは「トップの決断」ということで、当社にとって大きな決断は2001年4月に完成した大プロジェクトでした。福島県石川郡平田村に7万坪の山・谷を購入し、4万坪を整地して、間口80メートル、奥行き360メートルの第一工場を稼働させました。
この時のトップは私の父で、現会長(新井正準代表取締役会長)ですが、これを成功させるために、会長自身が福島県民、平田村の村民になると決め、妻である私たちの母を連れて移住しました。不退転の決意で取り組んだということで、当時、まだ若かった息子の私を送り込んで陣頭指揮を取らせるというのが一般的だと思うのですが、父は社運のかかったプロジェクトだからこそ自分で行くと決めた。これが経営者としての大きな決断だったのではないかと思います。
このプロジェクトの背景にあったのは1997年山一證券の倒産から2003年銀行に多額の公的資金を投入した、いわゆる"金融恐慌"です。
何故、そんな厳しい時代に?と思うのですが、会長は「こういう厳しい時こそ、中小企業にチャンスが巡って来るんや」と言っていましたが、最大の動機となったのは大手の取引先との正式契約が1999年に結ばれたことでした。これに対応するには郡山にあった、第一、第二、第三の3工場を1つにする必要がありました。これら3工場の合計は8千坪ぐらいになり、それ以上の敷地を平田村に求めたわけです。
会長は、平田村の村長さんの「何としても村民の雇用を守りたい」という強い思いに感銘を受けた、ここでならプロジェクトが成功すると思ったと言っていました。
私は副社長でしたが、7万坪の山・谷を前に、「ここを国か県が造成して工業団地を造ってくれるんですよね?」と聞いて、会長に「あほか、自分たちで造るんや」と言われたときは、腰を抜かすぐらいびっくりしました(笑)。
時代背景は金融恐慌で真っ暗闇、需要予測はあったものの金子、経済が伴わなければ進展しません。その金子を確保するために、会長は「北海道東北開発銀行」という国の銀行の仙台支店に飛び込み、「この時勢に、三進金属は福島県でこういう事業をしようとしている。事業費の半分を出してもらえないか」と掛け合いました。ここが会長の、トップの決断の非常に大切なところであったと思います。
そこは北海道と東北を開発するためにできた銀行で、民間の銀行とは違いました。
そのころは銀行の貸し渋り、貸しはがしが話題になっていたころですから、半分は民間ではなく国に、と考えたのです。しかし、銀行側としたら、飛び込みで来られて、事業費23億24億という金額の半分を貸してほしいと言われても、「大阪の付き合いのある銀行に行って下さい」と断りますよね。それでも父は何度も銀行に掛け合って、とうとう最後には支店長から「ところで、あんたは何歳ですか?」と年齢的に無理だと言われました。父は64歳、25年近く前の話ですから、会社人生の終わりかけです。それで、次の交渉のとき、私を連れて行き、「私が死んでも、この息子が責任を持って返しますから」(笑)。それで、支店長が根負けして借りることができたのです。
事業費はすべて借り入れでしたので、残りの半分(全額の2分の1)は、ふるさと活性化の資金を村から出してもらえるということで、これで2分の1の3分の1、つまり総額の6分の1をまかない、りそな銀行から6分の1、残りの6分の1を平田村の地元の銀行から借りるということで決着して、「これで行くぞ」となったときに、地元の銀行が「貸さない」となったのです。
スタートする直前の出来事で、計画全体が崩壊するかもしれないというぐらいの衝撃でした。必死の思いで大阪の住友銀行さん(当時)に駆け込み、事情を説明すると、支店長さんは非常に男気のある人で「わかった、稟議書なんか書いていたら間に合わない。いまから淀屋橋の本店に行って、役員に話をして来る」と行動を起こしてくれたのです。それで助かったのです。
しかも、条件として提示されたのが、「造成は熊谷組に任せる」ということで、我々としたら、建設・土木で日本一の会社に依頼できるという願ってもない展開になったのです。
7万坪の土地を熊谷組さんに造成してもらえたというのは、当社の大きな幸運であったと思います。その土地に建てた、間口80メートル、奥行き360メートル、8600坪の大工場は橋梁メーカーの川田工業さんに建ててもらいました。間口80メートルのところに3本しか柱が建っていない、といったようなことができたのは、やはり橋梁などを手掛けている会社だったからです。
東日本大震災では肝をつぶしましたが、超一流の会社に依頼したおかげで、土地も工場もまったく被害がなく、罹災証明も出ませんでした。そういう強運もありました。

■リーマンショックで一転、賞与ゼロ、給与カット、人員削減も…
福島工場が完成したのが2001年で、大震災が2011年、その10年間のうち2007年までは非常に好調に推移しました。
2007年9月の決算では、199億7500万円まで伸長。2001年の段階では130億円ぐらいでしたから、右肩上がりで、「福島工場を稼働してよかった、来年は200億円だ!」と言っていた矢先、リーマンショックで一気に60億円近く下がる、というとんでもない事態に陥りました。これはいまでも忘れられない経験です。
2004年10月に私が社長に就任していましたので、トップは私です。2007年の時点では有頂天であったのに、そこから奈落の底につき落とされたのです。
そのころ、銀行やメインの仕入れ先から「社長、とにかく赤字にはしないで下さい」と言われていました。そのころには、もうコンピュータで分析や判断が行われるようになっていたので、経営が赤字になった企業には、手のひらを返すような対応になる、と言われていたのです。
それで、一大決心をし、社員に「申し訳ないけど、こういう状況だから」と説明し、賞与をゼロにし、なおかつ給与カットもしました。一般社員は5%、部長級は10%などの割合で給与カットした状態で2年5ヵ月を過ごし、その間に、雇用維持調整法ですか、それも大々的に取り入れ、やるべきことは何でもやりましたが、それでも間に合わず、とうとう雇用に手を付けざるを得ない事態になりました。
営業の人員と営業拠点を減らしたら、ますます苦しくなるため、工場の人員削減に踏み切り、福島工場では200名のうち半数の100名近く、これは派遣社員も含めてですが、辞めてもらう決断をしました。最後は、指名解雇までせざるを得なかったのです。そのときが2010年、苦しくなって3期目で、まだマイナス4億円でした。
それでも、年が変わって2011年になれば、マイナス2億ぐらいになれるかなと考えていた3月、東京の当時の支社長から電話がかかってきて、「社長、いま東京は自分が経験したことがないぐらいの揺れに襲われています、テレビをつけて下さい」と絶叫された。東日本大震災です。
■東日本大震災に続く原発事故、会長の決断は「ここにおる!」
そのとき、会長はたまたま福島から大阪に戻って来ていたのですが、「すぐに帰る!飛行機のチケットを取れ」と言って、無理矢理に乗せてもらったら、警察官と自衛隊の人しか乗っていなかったそうです。
そうして会長が福島に帰った翌日、福島の原発事故が起きました。
福島工場には当時20名ぐらいのベトナム人研修生がいて、本国から「成田空港に政府専用機を用意しているから避難したい人は集まって下さい」という情報が届いていました。
彼らに「自分たちはどうしたらいいのですか?」と聞かれた会長は「大丈夫だ」と言い切ったのです。その根拠は原発事故の現場から、福島工場は45キロ離れていて、避難指示が出ていたのは35キロ圏内だったこと。5キロ圏内から10キロ圏内…と避難地域が拡大していきましたが、35キロ地点でぴたりと止まったのです。
そのとき、会長は「自分がここにおるんやから大丈夫や」とも言っていました。経営者が真っ先に避難したところもありましたから、説得力があったと思います。3ヵ月後に帰国が決まっていた4名は帰りましたが、16名は残って仕事をしてくれました。おかげで、塗装ができていなかった仕掛りの物件を無事に仕上げることができたのです。
塗装を彼らに任せていたので、研修生全員が帰国してしまっていたら困った事態になるところでした。
原発事故後、会長は自宅には帰らず、ずっと工場の社員寮に泊まって、夜になると、鍋大会をしていたようです。「ベトナムの鍋がうまいか、日本の鍋がうまいか。水はないけど、ビールはある」とか言って(笑)。
そのビールを飲み過ぎたのか、6月に食道ガンが見つかりました。それも、会長の強運だったと思っているのですが、母が胃カメラを飲みたくないと言うので、会長が「俺も一緒に胃カメラを飲むから、二人で検査に行こう」と無理矢理予約を取って、産業医の先生のところへ行ったら、母は問題なしで会長にガンがあると。大手術になると言われ、たまたま、私の妻の弟が神戸大にいたので、そこで8月のお盆休みに食道全摘手術を受けました。
10月に退院したときは、髪の毛も3分の2ぐらい抜けて、声も出ない、杖なしでは歩けないという状態で、「自分の人生はここで終わる。思い描いていた福島第三工場と、夢であった研修センター(「緑正館」)は何とかお前たちで達成してほしい」と私と弟に言っていました。
それが、年が明けた2月、原発事故から1年という時期に、「福島復興補助金事業」が発表されたのです。
会長からいきなり、「大変や、事業費の3分の2を補助してくれるらしいぞ!」とそれは元気な声で電話があったのです。「まさか、そんな補助金ありませんよ。金利の3分の2じゃないですか」と私が言うと、「お前の言う通りやな。もう一回確認するわ」と声も小さくなって(笑)。それが2、3日後に本当だとわかった途端、急に元気になって、歩けなかった人間が歩けるようになり、出なかった声が出るようになり、髪の毛まで元に戻ったのです。人間の治癒力のすごさをまざまざと見ました。
福島第三工場は2000坪で、その設計を1ヵ月半で描かないといけないということになったのですが、第一、第二を手掛けてくれた川田工業の次長さんが「そんな短期間で無理ですよ」と言われたけれど、会長が「大丈夫や。第二工場と同じでいい。キミだったらできる!」と言って、やってもらったんです(笑)。
それで第三工場ができ、研修センターの建設にも取り掛かりました。会長の思い描いていたのはログハウス風の建物で、それには3億円の予算をオーバーして5億円かかるということで、ログハウスは諦めて、発注しかけていました。
そのときに、福島復興の補助金事業で、阿武隈川流域の木材を使って建設をする分には補助金を出すということがわかったので、それに手を挙げたのです。除染作業は住宅地や公共施設のある場所に限られ、山野まではできない。そのために、福島の林業、木材関係は大打撃を受けていました。その救済のための補助金事業でした。

条件は、公民館としても使えるように、ということで、工場の敷地内の公民館という珍しい建物が福島で初めて誕生しました。
福島工場が2001年に稼働を開始したときから、会長はポケットマネーで桃やリンゴ、栗の苗木を50本、100本と買ってきて、「工場を森のようにしたい」と植えていました。
工場で働く社員の憩いの場所に、と地道にやっていたことなのですが、2014年にはそれらの苗木が立派に育っていました。工場見学にお客さんや地元の小学生らを招き入れたりしていましたから、そういった活動も評価されて、福島工場が「緑化推進功労者内閣総理大臣賞」という大変名誉な賞をいただき、天皇・皇后両陛下から直接お褒めの言葉をいただくことにもなりました。

会長は、「CSR」企業の社会的責任といった言葉が一般的になる前から、地域に貢献していくという考え方で、それが大きな流れとなって、私たちの会社を導いてくれたと感じています。それは福島工場だけではなく、大阪府泉北郡の忠岡工場でも、周りに木を植えたり、池や滝を造ったりしていて、それが前例となって福島でも、と取り組んだのです。
忠岡では、1988年に「国際交流基金」として忠岡町に寄付しており、いまでも中学生が提携しているオーストラリアの学校と交換留学生の形で交流しているようです。たまに、学校の先生からお礼を言われます(笑)。
福島では震災後、耕作放棄地がほかの地域より多くなっているため、県やJAが一生懸命、「企業さんが農業法人をつくって、田んぼを維持してほしい」とアナウンスをしていましたので、当社は10町歩、3万坪の放棄地を借り受けて、お米づくりを始め、去年の秋には37トン、その前は40トン収穫しています。「サンシン夢ファーム」という農業法人を設立して、運営しています。

このお米はまったく販売していなくて、東西両工場にある社員食堂で提供しています。これも、会長の社員に対する思いで、「しっかりご飯を食べなければいかん」ということでやっています。なおかつ、当社は植物工場も展開していますので、愛知県弥富市でつくった無農薬野菜も社員食堂で提供しています。「エム式水耕研究所」という子会社にしているので、そこから購入しています。
社員の健康増進ということでは、2020年1月に会長が「健康宣言」をしました。会長の片腕だった常務が肺ガンで亡くなり、たばこを吸うことを止められなかったと悔やんで、会社の敷地内では禁煙、と宣言したのです。私は、たばこを吸う社員が多いから反発されるだろうと心配したのですが、2月に横浜に停泊している豪華客船からコロナ患者が出たというニュースが流れ、「たばこは吸わない方がいいらしい」となって、一気に受け入れられました。
「ホワイト500」「ブライト500」というのは健康経営優良法人認定制度で、ホワイトは大企業、ブライトは中小企業向けで、それぞれのトップ500社が認定されます。当社は4年連続で「ブライト500」に認定されています。
昨年来の令和のコメ騒動では、社員から感謝されました(笑)。会社の成長は、社員の成長とともに、という考え方を昔から貫いて、会長の持ち株は全部、社員持ち株会に譲渡しました。幹部社員が株を持ち、卒業したら、次の幹部社員に渡していくというかたちです。
■決算賞与や社員と会社の情報を共有する取り組みで活性化
私は社長就任2年後の2006年に合理化協会のSMS「あべ塾」に入会していますが、これも決断の一つだったと思います。普通はなかなか入らないと思います(笑)。
非常に厳しい勉強会で、だれでも入れるわけでもなかったですから。それに私は大きな声を出して、自分や人を鼓舞するなどということが大嫌いで、そういう訓練もある、みたいなことを聞いて、躊躇したのですが、よくよく内容を吟味したら、「自分がバトンタッチして、会社の次の成長を確かなものにしていくためには、ここで鍛えてもらう必要がある」とわかったのです。
1999年から取引が始まったトヨタ自動織機さんには月に1回、「トヨタ工程改善の勉強会」があって、これと相通ずるものがたくさんありました。両方とも厳しくて、社員が何人か辞めていきましたが、残った社員がいまの当社を支えてくれています。
2006年以降ですが、会社の現状を社員全員にわかっておいてもらう必要がある、ということで、「サイネージ」で情報を流すようにしました。毎月、支社と会社全体の成績を発表し、行事などの情報も伝えるようにしています。これをしていたことが、リーマンショックのときに、大変な決断をするに当たって、社員の深い理解を得られたのではないかと思います。
私が社長になってからスタートしたものとして、決算賞与のシステムがあります。冬1.5ヵ月、夏1.5ヵ月をベースとして、プラスαを10月末に決算賞与として出すというもので、8月末の成績で判断しようということで、2億円単位で0.5ヵ月ずつ分ぐらいプラスαする、ということでやっていて、55期には3ヵ月の決算賞与が出せて通算6ヵ月ですから、みんな喜んでくれました。あべ塾では賞与は5ヵ月、6ヵ月を目指せと言われていましたから、達成できて私も嬉しかったです。
ただ、その翌年には鋼材が76%も値上がりして、どうしようもないなかで、1ヵ月の決算賞与が出せて通算4ヵ月、次の年も4ヵ月でした。
今年は、最初に1億円の不良債権をつかまされるというハプニングがあり、決算賞与を1ヵ月も出せないのではないかと思っていたので、単位を2億円ではなくて100万円に下げて、100万円で0.0025ヵ月出す、と発表しました。そうしたら、業容が非常によくなって、過去最高の決算賞与を出すことができました。
社員の資格取得についても力を入れていて、40年ぐらい前に自走式の駐車場を手掛けるようになり、建築士の資格を持った人間が必要となったことがきっかけで、自分たちで勉強会をするようになりました。知り合いに講師を頼み、3年間で14名が2級建築士の資格を取りました。一人はさらに勉強して1級建築士の資格も取り、本社の1級建築士事務所の金看板はその彼の名前になっています。
営業マンも、電動の移動ラックの施工のときに、お客さんに適切なアドバイスをするためには知識が必要ということで、2級施工管理士の資格をきっちりと取るように推奨しています。当然、資格を取れば資格手当を出しています。
トップの決断ということでは、私どもの会長は、それは大きな決断をいくつもしていますが、けっして無謀なことはしていません。
大阪市内の小さな工場から、忠岡に大工場を建設したときも、行政の施策で市内の工場を郊外に移す場合は特例があって、それを利用し、市内の工場を売却した利益を元手にしています。福島に工場を設けたのは、「東に向かって走るトラックが半分以上」であったため、東に工場をもつ決断をし、需要見込みもありましたから無茶なことではなかったのです。
「あんなことをして三進はつぶれる」と同業者に言われましたが、つぶれたのはバブルのときに本業以外のことに手を出したところです。本業に地道に取り組んで、いざというときには大きな決断を下す。それが数々の幸運を引き寄せ、2040年には300億円企業を目指すところまで拡大、成長できた要因になっていると思っています。